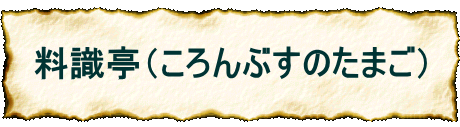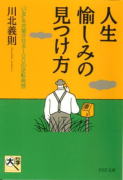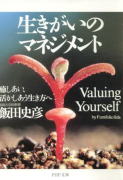「足を知る」は難しいことです。
何かにつけて「良い」とか「悪い」とかの判断をしていると、一生「足を知る」にはたどり着けないのでしょう。
「足を知る」は“良い・悪い”という判断をしないことなのでしょうか!
何かにつけて「良い」とか「悪い」とかの判断をしていると、一生「足を知る」にはたどり着けないのでしょう。
「足を知る」は“良い・悪い”という判断をしないことなのでしょうか!
か21-03
川北義則
砂漠の真ん中で水筒に半分くらいの水しか残っていないとき、「もう半分しか水がない」と考えるか、「まだ半分残っている」と考えるかによって、生死が左右されるという。「まだ半分水が残っているから、大丈夫、なんとか生きられる」と信じれば、生き抜く気力が湧き、砂漠を乗り切ることもできる。このような考え方が、よくいわれるプラス発想なのである。
では、どうすれば愉しいプラス発想ができるか。それには普段から、発想の転換をするクセをつけておくとよいだろう。要はいかに、頭をやわらかくおくかだ。
では、どうすれば愉しいプラス発想ができるか。それには普段から、発想の転換をするクセをつけておくとよいだろう。要はいかに、頭をやわらかくおくかだ。
ヒ03-01
ひろ さちや
仏教の発展は小乗から大乗へといわれ、それは出家者のみならず在家者にも仏の教えが聞かれねばならないということであるが、根本は一部のエリートだけでなく、すべての人がしあわせにならねばならぬというオシャカさまの願いの表われということができる。わが国の仏教は大乗だが、今の日本はこれと反対の優勝劣敗の原則に支配されている。それへの批判が弱者の側に立とうとの著者の姿勢を打ち出させることになる。
その大乗仏教が示す根本的な生き方が、本書の主題六波羅蜜である。
その大乗仏教が示す根本的な生き方が、本書の主題六波羅蜜である。
い38-02
飯田史彦
自分という存在の価値……誰もが、それを自分自身の力によって、発見したり、想像したりできるようになれば、毎日が「生きがい」に満ちたものになるのではないか……そして、同じように、自分以外の人々の価値も発見したり、想像したりできるようになれば、嫌ったり憎んだりせずにすむのではないか……自分の考えは、甘すぎるのかもしれないけれど、きっと世界中に、同じ考えの専門家たちがあふれているはずだ……。こうして私は、「生きがい」を探求する旅の途中で、ここでもまた、新たな宿題を与えられました。